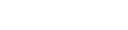フルマラソン完走!次は何する?と迷う人が挑むウルトラマラソンなるもの
- 2019/09/09
-
 ライフスタイル・娯楽
ライフスタイル・娯楽 - 560view
- スポーツ
- スポーツ
- マラソン
- ランニング
- 趣味
フルマラソンは誰でも走れるよ、と口にする人は多い。あるいはそうかもしれない。2007年に始まった東京マラソンがきっかけで盛り上がった日本のマラソンブームには多少陰りが見えてきたと言われているが、それでも日本各地で毎週末のようにマラソン大会が開かれている。もはや42キロを走ることは特別なことではなく、アスリートではない数多くの一般男女が自分もやってみようと思えるぐらいに身近なものになった。
だが、どれだけ多くの人が既にやっていることだとしても、42.195キロという距離を自分の足だけを頼りに走り切る ―多少は歩くにしても― のは、やはり容易なことではない。誰でもやれば出来ることなのかもしれないが、誰もがやろうとするわけではないのがフルマラソンだ。スタートラインにつくまでに、ある人は何か月も、場合によっては何年もトレーニングを積まなくてはいけない。それに費やした時間と汗こそがマラソナーの勲章であり、タイムがどうあれ、すべての完走者は勝利者である、とぼくは思う。
フルマラソン完走という偉大な達成を成し遂げた。さあ次はどうしよう?と迷う人がいる。もちろん、来年もこのレースに出て今年よりも速いタイムを目指すぞ、というのは立派なモチベーションだ。初マラソンに5時間かかった人が、次はサブ4(4時間以内)、さらにはサブ3(3時間以内)へと完走タイムの目標を次々と高めに設定していくのは、ある意味ではランナーとしての王道でもある。
タイムを速めるのではなく、さらにもっと長い距離を走れることが自分にできるだろうかと言う方向に舵を切る人もいる。世の中は便利だ。フルマラソン以上の距離を走るレース、ウルトラマラソンという新たな挑戦の場がそんな人たちにちゃんと用意されている。
ウルトラマラソンとはマラソンより古い?

そもそもフルマラソンはなぜ42キロなのかと言えば、よく知られているのが紀元前450年のマラトンの戦いにまつわる話である。この戦いに勝利したアテナイ軍はフィディピディスという兵士を母国までへの伝令にした。フィディピディスは戦場のマラトンから約40km離れたアテネまでを完全装備のまま走りぬき、「Nike!(勝利)」と叫んだ直後に地面に倒れて息を引き取った。
この故事にちなんで、第1回オリンピックではマラトンーアテネ間約40キロを走るレースが競技に加えられた。その後の紆余曲折があって、現在の約42.195キロに落ち着いた。
マラソンの由来とされるこの話に比べると、あまり知られていないことではあるが、フィディピディスが走ったのは実は40キロだけではない。そもそも走ることが専門の兵士が、たかがそれぐらいで死ぬわけはない。実はこの戦いの前、フィディピディスは援軍を求めるための伝令として、アテネからスパルタまでの246キロを一日半で走ったとされているのだ。古代ギリシャの歴史家ヘロドトスが書き残したエピソードだ。本当にそんなことが人間に出来るのかと疑問に思った英国空軍の兵士らが1982年に実際に試してみたことが、最も過酷なウルトラマラソン・レースの1つと呼ばれるスパルタスロンの始まりだ。
歴史的に言えば、実はフルマラソンよりウルトラマラソンの方がマラトンの戦いを起源とするには相応しいのだ。
日本はウルトラマラソン大国

246キロのスパルタスロンは人間の極限だとしても、それ以外に世界的な有名なウルトラマラソン・レースには100マイル(約160キロ)のものが多い。フランスのウルトラトレイル・デュ・モンブラン(UTMB)、アメリカのウェスタンステイツ・エンデュランスランなどがそうだ。
フルマラソンの約4倍となると、これは普通の人がおいそれと試せる距離ではない。大体、1日で走り終わらないのだから、不眠不休で夜中にヘッドランプをつけて走ることになりかねず、もはや長距離走の範疇には収まらず、人間の限界に挑むサバイバルレースの様相を帯びてくる。
いきなりそこまでは無理だとしても、フルマラソン以上の距離に挑戦してみたいと言う人には50キロ~100キロのレースがある。そして嬉しいことに、日本はこの100キロ以下の比較的穏当なウルトラマラソンのレースが実に多いのだ。
最も有名なのは北海道のサロマ湖100キロで、このレースでは同距離の世界記録を男女とも日本人ランナーが樹立している。四国の四万十川100キロも風光明媚なコースで人気がある。海外でのウルトラマラソンは同時に山間部を走るトレイルランであることが多いが、日本国内ではサロマ湖や四万十川のように一般道路を走るレースが多いので便利だ。
一般道路のレースではエイドステーションが充実しているので、ランナーは何も持たずにただ走ればいい。完走できなくなったら、収容バスに乗って帰ればいい。100キロ走の制限時間が12~14時間ぐらいのレースが多く、早朝に走り出せば、なんとかその日のうちには走り終えることができる。道に迷ったら遭難しかねないトレイルランとは異なり、基本的にはフルマラソンの延長線上にあるのだ。
ウルトラマラソンは中高年向き
2018年のサロマ湖100キロで世界記録となる6時間09分14秒のタイムで優勝した風見尚選手は1983年生まれで、レース当時は35歳だった。女子の部で優勝した藤澤舞選手は43歳だった。藤澤選手は2019年にも4度目となる優勝を飾っている。
他の有名なウルトラマラソン・レースでも40代以上の優勝者や上位入賞者が実に多い。2013年と少し古いデータだが、Journal of Strength and Conditioning Researchが報告したところによると、ウルトラマラソン完走者の平均年齢は43歳、最初のウルトラマラソンに挑戦する平均年齢は36歳だということだ。ちなみに、前述の246キロを走った後でさらに40キロを走って死んだ古代ギリシャの兵士フィディピディスは享年40歳だった。
実際にレースで走って周りを見渡しても、ウルトラマラソンはフルマラソンより年齢層が高いな、とはよく思うことだ。かく言うぼくも、初めて50キロを走った時は47歳だったし、初めて100キロを走ったとき50歳を目前にしていた。平均より少しは高いかもしれないけど、自分が飛びぬけて年上だとは感じなかった。ぼくより年配のランナーもたくさんいた。
ちなみに走る距離が長くなればなるほど男女のタイム差は小さくなるようで、自分よるはるかに年上とおぼしき女性に追い抜かれることもあった。例えば、腕相撲で自分の母親に負ける男性はあまりいないだろう。だが、ウルトラマラソンではそれがあり得る。
なぜウルトラマラソンに年長者が多いのかについては様々な理由があると思う。長い距離を走るための筋肉を作り上げるには時間がかかるから、ということもその1つ。精神的な耐久力も見逃せない要素だ。何しろ、朝から晩まで半日以上、ひどいときにはもっと長い時間を、ただひたすら走り続けるのだ。好奇心が強く、あれこれと興味が移る若い頃には、まず向かないだろう。
ウルトラマラソン対策に答えはない

それではウルトラマラソンを走ってみようと思い立ったとき、どんな準備をしたらよいのだろうか? その疑問に答える確立された方法論というものは実はほとんどない。書店でスポーツ関連のセクションを覗いてほしい。フルマラソンの対策本や入門書はたくさん並んでいても、ウルトラマラソンのそれはあまり見当たらないのではないか。もちろん絶無ではないだろうが、少なくともぼくは見たことがない。
マニュアルがないわけだから、ウルトラマラソンに挑戦する人は、誰か経験者に対策方法を尋ねるか、あるいは自分で工夫するしかない。そのことに不安を覚える人もいるだろうし、かえって面白いと感じる人もいるだろう。ぼくは完全に後者だ。自分の頭で考えたことを自分の体で試す。こんなに楽しいことはない。失敗したところで、自分の体が痛むだけで、誰に迷惑がかかるわけでもない。こういう考えをもつタイプのランナーにはウルトラマラソンは恰好の趣味になる。何しろ、50キロ走ったら、次は100キロ、それで飽き足りなくなったら160キロ、といくらでも挑戦の場が設けられているのだ。そんなことをして何が楽しいの?と思う人はそもそも長距離走には向かない。
そのような性格なものだから、ぼくが100キロ走に生まれて初めて挑戦した時は、せっかくだからあまり世の中の人がやらない非常識な方法を試してみようと考え、実践した。普通の人はウルトラマラソンなのだから走行距離を増やすだろうと考えて、あえて逆をやってみたのだ。要約すると以下の方針でレース前の3か月を過ごした。
• 月間走行距離は100キロ以下
• 走るのは週3,4回
• 残る3回はクロスフィット
• 1回に走る最長距離はハーフマラソン(21キロ)まで
• 普段の食事は糖質制限。米、パン、麺類は一切食べない
• カーボローディングは一切行わない
ちなみに以前ぼくが書いた記事「スポーツをするなら、酒を飲むのがどれだけろくでもないことか」を読んでくれた人には、この3か月間ぼくは一切のアルコールを口にしませんでした、と伝えておく。
結果として、100キロを制限時間内に完走することができた。練習でも本番でも故障は1回もなかった。もちろん大したタイムではなかったし、このやり方がベストであると主張しているわけでは決してない。ただ、こんな風に自分なりのやり方で自分の能力を試す機会は他にめったにないよと言いたいのだ。ランナー1人1人、それぞれが別のやり方であっても構わないと思う。この1文を読んでウルトラマラソンに少しでも興味を持ってくれた人がいれば、それに勝る喜びはない。
![オヤジを“カッコよく”するYAZIUP[ヤジアップ]](https://yaziup.com/wp/wp-content/themes/yaziup/img/logo-black-yaziup.png)