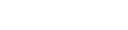海外ドラマの1クール製作費は火サスの5倍?日本の2時間サスペンスがつまらない理由
- 2019/03/23
-
 ビジネス
ビジネス - 525view
- 国際情勢
- お金
- ドラマ
- 国際情勢
- 広告
- 日本
- 海外
バブル世代お馴染みのドラマといえば、民放各社午後9~10時から始まり、3カ月で終了になるトレンディドラマ。
が、その親世代お馴染みのドラマと言えば『火曜サスペンス劇場』に代表される様な、2時間サスペンスだ。
’85年には週8つも放映枠があり、サスペンスを放映しない時は映画をやっていたこの時間帯。
今では殆ど消滅してしまってるのは、視聴者のテレビ離れが原因ではない。
視聴者のテレビ離れの食い止めに、’80年代から本格的に取り組んだ米国と日本では、番組作りに仕組みはどう違うのか。
昔のお茶の間の主婦をターゲットにした2時間ドラマ

元電通社員で、阪南大教授(放映文化論)の大野茂氏によると、日本の民放2時間サスペンスは、’77年にテレビ朝日で『土曜ワイド劇場』が始まった事だった。
’60年代後半から、今もなお米国で作り続けられている『テレビ映画』や『パイロット版』を参考にして作り、『土曜ワイド劇場』がお茶の間に受け入れられたのをきっかけに、オープニングテーマが独特の『火曜サスペンス劇場(日本テレビ系)』が参入。
’85年には民放のみならず地方局も参入し、8局の放映枠があり、視聴率は最高で
NHKの朝ドラ並の30%を記録していた。
何故人気だったのか、そして廃れた理由はと聞かれると、2時間ドラマの視聴者の年代層は後期高齢者だからだ。
2時間ドラマが始まった当時、共働き主婦も、専業主婦も今程気軽に旅行には行けなかった。
そんな時に自分たちと同世代の俳優たちが、ドラマの舞台で温泉や観光地を巡り、事件を解決していくという筋書きは魅力的に映ったとも言える。
この様な時代背景から、船越英一郎や山岡紅葉の様な『2時間ドラマ俳優』を生み出した。
だが時代の流れには逆らえない、日本の2時間ミステリー及び、民放ゴールデンタイムの2時間枠が消えるには以下の理由がある。
1:同じミステリー作家が原作で、俳優の顔触れも同じ
2:温泉地や観光地がロケ地になるなど、展開が見えている
3:予定調和でベタな展開
4:女性や男性の描かれだけでなく、上司部下、親子関係の描かれがステレオタイプ
5:同じ時間帯にドキュメンタリーか映画をやってほしい
6:予算に見合わない
ミステリー作家を養成できなかったというのは日本にとって痛手だ。
毎回、山村美沙や、西岡京太郎など決まりきった作家に原作を依頼してきた事から、
話の筋書きや配役が同じになり、視聴者離れするのを拒めなかっと言える。
民放のBS局の昼間にサスペンスの再放送をやっているが、これは視聴者が現在の
後期高齢者になっているのを見越してだと思われる。
定期的に主演俳優が変わったのは内田康夫氏原作の『浅見光彦シリーズ』ぐらいではないだろうか。
日本テレビ、TBS、フジテレビで放映され、歴代浅見光彦として、水谷豊、辰巳琢朗、榎木孝明、沢村一樹、中村俊介、速水もこみち、平岡佑太と、他局の人気ドラマでも通じる俳優を輩出しているのが特徴だ。
では日本のドラマの作り方と、海外のドラマの作り方、決定的に違うのは、どういう事か。
海外ドラマ1クールの予算は、日本の映画1本分
日本と海外では、ドラマにかける予算の割合及び、作り方そのものが違う。
競争率が激しい米国のドラマは制作会社が全国の放映局(ネットワーク)に向けて先に作品を作る。
まず1話・1~2時間のパイロット版を作り、その販売権を放送局に買って貰うシステムになっているのだ。
初回放送だけでなく、再放送権も競売にかけられるため、一度放映が終わった作品でも、人気があれば市場に出す度に金を生み出せる。
放映途中の作品から派生したスピンオフを作る度に、金を生み出せるのが米国のドラマの作りだ。
収入も日本の様に広告収入に頼るだけでは行き詰まると考え、’80年代から衛星放送に力を入れていたので、9割の家で有料チャンネルが見れる。
日本でも既に多くのユーザーに支持されているHuluは、元々米国の大手テレビ局がテレビ離れを危惧して作ったもの。
ネトフリはビデオレンタル店で現在のCEOが『アポロ13』の延滞料を払わなくてはいけない羽目に陥り、家でも見放題を楽しめないかと思い付いたのがきっかけだった。
こうしてテレビ離れ、メディア離れを食い止め、収入減が広告だけでなく、ライセンス料、各提供媒体の会費もあるので、人気ドラマの制作費は、それだけ膨れあがる。
現在日本の地方局で放映されている『CSI:科学捜査官』は、スピンオフの『CSI:NY』、『CSI:マイアミ』も含め、1クールの製作費は3億円と言われている。
『CSI:科学捜査班』は一時期視聴率のテコ入れの為に『マトリックス』や『ミッション:イッポッシブル』のローレンス・フィッシュバーンを主役に据えたほどだ。
スピンオフと本編の全出演者が出そろったエピソードを作る事を、米国では『クロスオーバー』というが、CSIの場合は、スピード感もあり、製作から10年たった今みても見ごたえがある。
現地オールロケをする事で、テレビドラマが収益をもたらす例もある。
『HAWAI-FIVE-O』は、オールハワイロケだが、収益の6割がハワイ州にもたらされるという。
だが近年製作費の高騰で、撮影が思う様に進まず、視聴率が以前に比べ落ちているというのも拒めない。
反対にドラマから映画に出世する俳優もいる。
『ブレイキング・バッド』で有名になったブライアン・クランストンは、’80年代鳴かず飛ばずだったが、この作品で一気に有名になり映画に進出。
『ゲーム・オブ・スローンズ』のオブリン役で有名になったペドロ・パスカルも『イコライザー2』で、デンゼル・ワシントンの向こうを張った。
この様に、海を渡った向こうは、1クールに億単位の金をだすだけの価値があると見込まれるものがある。
その一方で、日本はサスペンス劇場にかける製作費がいくらか、また映画一本にかける製作費がいくらになっているか、ご存じだろうか。
実は破格の金がかかるサスペンスドラマ
日本のサスペンス劇場にかける製作費は、4500万から5000万である。
製作現場に居た知り合いから聞いた話なのだが、視聴率も落ち、スポンサー探しも大変になった現在、割が合わないのが現状だ。
私の両親は広告代理店の営業部に居たが、代理店としては若くて購買欲が強い層が観てくれる媒体に広告を流そうと思うのはいつの世の中でも変わらない。
この時間帯にサスペンスが作られて、放映されている事をもったいないと思う人も多いのではないだろうか。
かといって短時間で安くつくれるバラエティばかりがゴールデンタイムに放映されてしまうと、民放のクオリティそのものが落ちてしまう。
日本も米国の真似をすればいいかと言えば、そういうわけでもない。
近年の織田裕二のドラマがその典型的な例だ。
『踊る大捜査線』は単発ではいいドラマだったが、映画、スピンオフ、クロスオーバーと作り続ける度に、織田のオレオレキャラが全面に出すぎて駄作になってしまった。
海外ドラマ『SUITS』の日本版も、そっくりそのまま日本に書き換えただけで、新鮮味もなかった。
日本のトレンディドラマの黄金期を支えた俳優を主演に据えて、米国のマネをすればいいというものではないし、製作費の安いバラエティに頼ればよいというものではない。
視聴者離れを防ぐ並外れた創意工夫と予算をかける事は海外に学ばなければいけないのではないだろうか。
![オヤジを“カッコよく”するYAZIUP[ヤジアップ]](https://yaziup.com/wp/wp-content/themes/yaziup/img/logo-black-yaziup.png)